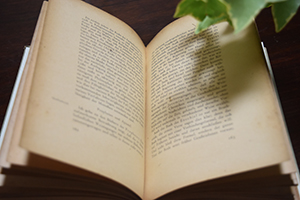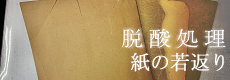製本について
製本にはさまざまな種類や形式がありますが、ここでは当社での代表的なものをご紹介致します。
●上製本(ハードカバー)
しっかりとした厚い板紙に手触り重視の表紙で、上質の書籍に用いられます。
一般的にハードカバーといわれている製本方法です。
布や皮・紙などでくるんだ厚紙を芯にした表紙を使用し,表紙は中の本よりもひとまわり大きく、中の本を保護する事ができます。
弊社では通常ミシン綴じを使用しております。
表紙や背に、文字や図柄などを金や銀色の箔押しをすることにより豪華さが際立ちます。
また上製本には背の形状の違いから角背製本と丸背製本の2つの様式があります。
●並製本(ソフトカバー)
表紙をソフトカバーを使用した本です。
中身を綴じ、表紙と接着して両方を同時に仕上げ断ちするので、表紙と中身は同じ大きさになります。
雑誌やカタログ・パンフレット・文庫本に多く用いられ、上製本に比べてコストを抑えることができます。綴じ方は、無線綴じ、平綴じ、中綴じなどがあります。
その中でも無線綴じは他の綴じ方とは異なり、針金や糸などを使用せずに、本文部分の背を接着剤で綴じられたものです。本の背中に強力な糊を付けて、表紙でくるむことから、“くるみ製本” とも呼ばれます。
●くるみ製本(ソフトカバー)
中身と表紙を別に作り、背を接着剤で固め、一枚の表紙で中身をくるむように製本したものです。
背以外の三方を断裁して仕上げます。
背にタイトルや名前などを入れることが出来ます。
●クロス巻き製本
背の部分に装丁用のクロス(布地)を巻きつけて強度を持たせる製本方法です。
簡易的に修理をする場合などにも使用します。
●観音製本
1枚ずつ折って貼り合せ、折り山を糊付けする方式です。
図面などに使われます。
●ビニール製本
透明な塩ビ・PPやOPPを表紙に使用します。
綴じ方の種類
●ミシン綴じ
本の中心を主にミシンでジグザグ縫いをして接着剤で固めます。
弊社が創意工夫をして、この工法を開発。普及努力を重ね、図書館製本業界に定着させました。
このとじ方を使用すると、本がとても丈夫になり、
またページの開きが良く複写作業が容易に出来やすくなります。
印刷面積を多くとることができ、見開きページとして写真など大きく掲載することができます。
弊社は、上製本に通常このとじ方を使用しております。
ページ数の少ない用紙の厚い絵本やアルバムにも利用されています。
●糸綴じ
本の中身がバラバラにならないように折丁を互いに連結させ、
丁合いされた巻頭の折丁から最終折丁までを糸を使って綴じ合わせます。
手綴じと機械綴じの2種類あります。
●平綴じ
接着剤を使わないで、針金を使って閉じます。
ページの少ないカタログやパンフレット、雑誌などで使用します。
●中綴じ
表紙と中身をまとめてホチキス針でとめる方式です。週刊誌などに使われています。
●無線綴じ
古い本など加工が難しい場合や、安価に作成する場合に選択します。
接着剤だけで折り部分の背を接合します。
●打ち抜き綴じ
紙を揃えて背寄りのノドぎわに穴を数箇所開け、開けた穴に紐を通して綴じる方式です。
●和綴じ
日本形式の製本方法です。
日本の熟練した職人の手作りで綴じられていきます。(用途:古文書、過去帳など)



写真左:ミシン綴じ、写真中:糸綴じ、写真右:打ち抜き綴じ
紙のサイズと厚さ
紙には様々な種類やサイズがあり、用途に合わせて選ぶことが大事です。
箔押し

機械と金版により「熱」と「圧力」を与えて、素材に金箔・銀箔などの箔を圧着する加工方法です。 弊社では金型による昔ながらの伝統的な工法を用いています。熱だけの表面への転写によるものと違い、耐久性に優れています。